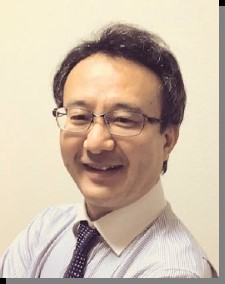建設部会のホーム![]() 行事案内
行事案内![]() 2025年4月 建設部会講演会(報告)
2025年4月 建設部会講演会(報告)
2025年4月 建設部会講演会(報告)
■日 時:令和7年4月16日(水)18:00〜19:30
■場 所:機械振興会館会議室(WEB開催あり)
■講 師:江副 哲 氏 弁護士、技術士(建設部門)
One Asia法律事務所大阪オフィス代表パートナー
■演 題:技術者倫理と企業倫理の相克〜不祥事の原因と対策〜
■参加者:会場29名(内訳:会員25名、非会員4名)Web参加者176名
■講演内容
(1) なぜ不祥事がなくならないのか
インフラ関連では、公的機関における官製談合、管理・監督義務違反による事故が少なからず発生し続けている。さらに、企業規模に関わらず、建設コンサルタントの設計ミスによる訴訟、ゼネコンによる談合事件や施工不良等が多数発生している。我が国の世界を代表する企業においても鉄鋼業や製造業の品質不正や自動車産業の検査結果の不正申請等が後を絶たない。これらに共通する原因のひとつに「安全を担う技術者が一般社会に対する責任よりも所属組織への責任や利害を優先した結果の不祥事」と考える。
(2) 不祥事の結末
不祥事の結末には、サンクションとペナルティがある。「サンクション(sanction)」は、ある言動に対して社会または世論(集団成員)が表明する、是か非かの一定の反応である。 是とされる行為には「承認・賞賛」等があり、非とされる行為には「制裁・処罰」等がある。「ペナルティ(penalty)」は、法律、ルールや契約を破った場合の罰を指す。企業の場合には、罰則適用(罰金)、許認可取消し、指名停止、損害賠償等が科せられる。行政の場合には、損害賠償義務等が科せられる。役員や従業員には、罰則適用(懲役、罰金)、損害賠償、懲戒処分等が科せられる。いずれにせよ信用失墜を免れることはできない。組織も個人も多大な損失を被り、失った信頼の回復も容易でない。
(3) 不祥事の原因分析
不祥事の原因は、次の3つに分類することができる。なお、次の分類は法的解釈と異なる部分があり、あくまでも分かり易く説明するためと理解頂きたい。
・故意事案:不正であることを認識しながら当該行為を行う(談合、不正の見逃し・隠蔽)。
・重過失事案:結果発生を容易に認識できたにもかかわらず、当該行為を行う(重大ミス)。
・過失事案:不正の認識、結果発生の認識はないが、ミス(過失)を犯す(不注意によるミス、ケアレスミス)。
(4) 不祥事へのアプローチ
「技術者倫理」と「企業倫理」に大別して考えてみる。
・故意事案:「技術者倫理」と「企業倫理」に対する組織の悪習
・重過失事案:「技術者倫理」と「企業倫理」に対する組織の理念・体質
・過失事案:「企業倫理」に対する組織の体制
技術者倫理と企業倫理を例えるならば「車の両輪の関係」と言える。
(5) 技術者倫理とは
・倫理:人間が社会生活を送って行くために従わなければならない道理
・一般企業人としての倫理:業務を行う上で備えるべきマインド。
・技術者としての倫理:高度の専門性を有する者が備えるべきマインドであり、より高度な倫理
技術者に高度な倫理が求められる理由には、「科学法則はウソをつけない、ウソをついてもいつかはバレる」、「ごまかしがきかない、結果は必ず目に見えて現れる」や「安全性をごまかすと、いつかは壊れる」等により、利用者の生命・身体・財産に多大な損失を与えてしまうからである。つまり、インフラや製品の危険性を把握できるのは、「技術者だけ」だからである。技術者がウソをつくと安全は、担保できないのである。利用者からすれば、技術者はインフラ・製品の安全を守る「最後の砦」である。このため、法令遵守(コンプライアンス)だけでは不十分であり、技術者倫理を備えなければならない。さらに、利用者から単なる言い分や押し付けではなく、客観的根拠に基づき「共感」を得られる説明が肝要である。
(6) 企業倫理とは
会社(法人)は、法律によって創作された虚構であり、企業体そのものに倫理は存在しない。組織内で業務に従事する人の倫理が経営判断につながる。では、なぜ個々人が技術者倫理を備えていても不祥事は生じるのか。経営判断の基礎は技術者倫理だが意思決定の過程によって変わるため、個々人の技術者倫理だけでは不祥事を防げない。即ち、技術者倫理と企業倫理の相克である。
(7) 不祥事事例の解説
個々人や企業のペナルティを考えると官製談合等のメリットは、皆無である。しかしながら、毎年、数件ある。なぜなのか。不祥事と技術者倫理の関係には、「設計ミスがないのに説明義務違反」が認められた事例がある。これは、裁判所も「設計者は技術者としてあるべき対応(発注者への説明)をすべきであった」と考えたからである。これは、「技術者倫理が法的義務に昇華した」と評価されたからである。裁判は、「一般人が考えるとどうなるのか」を考える。裁判官は、我々を専門家と認識していることを自覚しなければならない。
(8) 不祥事の防止策
業務の目的意識と業務内容の社会的影響を常に意識することが大切である。技術者倫理を備えていても、業務遂行に際して、質(業務の難易度)や量(業務量)により追い込まれるとミスや不正を犯してしまう可能性がある。さらに、チェック体制の強化にも限界があるため、部署内での円滑な意思疎通や認識共有が重要である。個々人としてのあるべき姿には、技術者倫理に反する行為の結果を認識し、「自律」した技術者として対応することが求められる。組織としてのあるべき姿には、自律した技術者が意思決定の過程で説明責任を果たし技術者倫理を経営判断に反映できる体制を構築することが求められる。
3 まとめ
弁護士かつ技術士(建設部門)である江副先生より、技術者倫理について講演を頂いた。法的視点より倫理と不祥事の関係を解説頂くことにより体系的かつ、階層的な構造でその関係を理解することができた。私見ではあるが、日常業務における「説明義務違反」への対策には、いわゆる清書された「打合せ簿」は、あまり効果が無い。一方、「日々のメールにより、やり取りの履歴を残すことが説明責任を果たすために寄与する」ことは、大変参考になる情報であった。技術が高度化・複雑化するなかで、技術者倫理の重要性は、日々高まっている。過去の事例や豊富なご経験より実例を交えてわかりやすくご講演いただき、多くの質問にも丁寧に応じていただいたことに感謝いたします。
【担当】長久保、三吉、岩部、影山(記)
このページのお問い合わせ:建設部会
「IPEJ」,「日本技術士会」,「技術士会」,「CEマーク」及び「PEマーク」は、公益社団法人日本技術士会の登録商標です。
公益社団法人 日本技術士会 / Copyright IPEJ. All Rights Reserved.