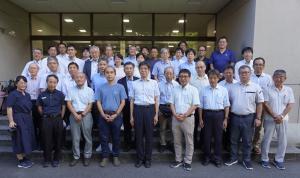生物工学部会のホーム![]() 部会活動状況
部会活動状況![]() 施設見学会実績(見学会および講演会)2024年
施設見学会実績(見学会および講演会)2024年
施設見学会実績(見学会および講演会)2024年
2024年度 施設見学会記録
【日時】2024年9月20日(金) 13:00-17:00 (終了後、懇親会)
【訪問先】山梨大学生命環境学部生命工学科 発生工学研究センター、大村智記念学術館、ワイン科学研究センター
【懇親会】山梨大学 大学会館
【内容】2024年度の夏季施設見学会は、山梨県支部との合同で同時見学会として山梨県甲府市の山梨大学で開催された。生物工学部門だけでなく、化学、森林、農業部門の方々に加え、山梨県支部の建設、機械、経営工学、上下水道、金属部門の方々も加わり、計36名の参加者であった。山村英樹会員(生物工学部会、山梨県支部、山梨大学教授)の開会の挨拶で幕を開け、引き続き山村会員から山梨大学、生命環境学部生命工学科のご説明があり、質疑応答を行った。次に、若山照彦教授(大学院総合研究部生命環境学域生命農学系(発生工学研究センター))のご講演、質疑応答があり、引き続き場所を移して発生工学研究センターの見学を行った。その後、大村智記念学術館を見学し、ワイン科学研究センターに移動し、久本雅嗣准教授(大学院総合研究部生命環境学域生命農学系(地域食物科学・ワイン科学研究センター))のご講演、質疑応答があり、見学を行った。
1.山梨大学生命環境学部生命工学科について(山村会員)
山村会員からご講演いただき、その中で2015年のノーベル生理学・医学賞受賞者である大村智先生の話もご紹介いただいた。大村先生は山梨県の韮崎市出身であること、さらには本年6月に研究組織「大村記念微生物資源研究フロウティラ」を立ち上げたことが紹介された。微生物資源を使って、薬剤耐性菌に対する新たな抗菌薬の開発などに利用する予定とのことである。微生物資源としては、放線菌ライブラリーがありスクリーニング系として有用であること、希少放線菌が多く含まれていること、地衣類、落葉、河川付着藻類、セミの抜け殻など非常に多様な分離源から菌を単離されていた。今は約4,000株の放線菌について特性情報、分類などを行っている。今後、革新的なアプローチとしてカルチュロミクス(culturomics)の手法も紹介された。この手法は様々な培養条件で網羅的に細菌を培養することで細菌を増殖させて同定する手法で、メタゲノム解析ではわからない細菌の少数集団(105CFU/g 未満)も検出することができる。この手法を並列的に大規模に実施し、選択培地にて多くの放線菌を単離することを計画している。このような選択的カルチュロミクスで得られた分離株から薬剤耐性菌への抗菌活性の有無の確認や全ゲノムシークエンスによる未知の抗生物質関連遺伝子の探索を行うことができるようになる。今後、MS-imagingもできればとのことである。
2.山梨大学 発生工学研究センターについて(若山先生)
若山先生の専門は哺乳類の生殖技術に関する研究であり、前職は理化学研究所の所属で、現在も引き続きES細胞 クローン、初期化、核移植、受精、遺伝資源の保存などの研究開発を行っている。特に精子のフリーズドライにおいては、室温で6年間保存可能な技術を有している。以前はガラスアンプル瓶で保存していたが、シート保存ができるようになっている。さらには宇宙での保存にもトライしており、2013年にはフリーズドライした精子を宇宙ステーションに持って行き、6年間保存後に地球に持ち帰り子供を作ることに成功している。地上で行ったX線照射実験により、精子は宇宙で200年くらいは保存できることが明らかとなった。また、受精卵を宇宙ステーションで培養する実験も行い、無重力であっても、地球の重力でも地上と同様に発生できることを証明した。一方クローン技術については、16年間凍結されていたマウスの死体からクローンを作ることや、マウスの尿中から回収した膀胱の細胞から核をとってきてクローンを作ることなどを行っていた。なお、核移植に必要なマイクロマニピュレーターは15セット保有しており、世界最大であるとのこと。フリーズドライで精子だけでなく体細胞も保存できるようになってきているが、卵子の保存はまだ誰も成功していない、クローンマウスではできてもクローンラットは作れない、鳥の体細胞クローンは誰もできてない、さらにはマウスの剥製からクローンを作るなど様々な知見が紹介された。
3.大村智記念学術館の見学について(山村会員)
大村智記念学術館は、1958年(昭和33年)に山梨大学学芸学部(現・教育学部)を卒業された大村智博士のノーベル生理学・医学賞受賞を機に、「山梨大学 大村智記念基金」を設立し、大村先生の偉業を称えその功績を末永く顕彰するため2018年に創設された。常設展では、大村先生の卒業論文や在籍当時の写真、数々の研究業績、ノーベル賞受賞に関する資料が展示され、大村先生の軌跡をたどることができた。これ以外にも、徽典館展示コーナーや山梨県名産の水晶の展示コーナーもあった。
4.山梨大学 ワイン科学研究センターについて(久本先生)
ワイン科学研究センターは3つの研究部門(発酵微生物工学研究部門、機能成分学研究部門、果実遺伝子工学研究部門)で構成されており、それぞれ約20名で、計60名ほどの教員、スタッフ、学生で運営している。久本先生はワイン中に含まれるポリフェノールの機能性に着目した研究を行っている。日本においてはワインが酒類の課税移出量に占める割合は約4%であり、経時的には少しずつ上昇傾向にある。一方、平成22年(2010年)にはワインメーカーは257であったが、令和2年(2020年)には447に増加しており、特に長野県、北海道で増えているとのことである。その他にはクラフトビールやクラフトジンが増えており、消費者ニーズの多様性の一面が酒類においても垣間見られる。最近は、アルコール関連問題への取り組みとしてお酒のパッケージには従来のアルコール度数に加え、純アルコール量の表示が進められている。ワイン醸造のワイン製造以外の活用としては、ワインの搾り粕を用いてクロロエテン類で汚染された土壌を浄化するバイオレメディエーション(Bioremediation)があり、地中微生物の嫌気発酵を用いた脱塩素化にトライされていた。この脱塩素化には微生物が作る有機酸が関与している(水素供与体となる)ことなどが紹介された。
5.懇親会
山梨大学の構内の大学会館にて、懇親会が開催された。山梨大学 生命環境部生命工学科の微生物機能・生態応用工学分野の大槻隆司准教授、中川洋史准教授も参加された。東田部会長の乾杯から始まり、盛況の内に幕を閉じた。
6.所感
今回の見学会については、山村英樹会員、そして奥様の山村裕美会員(山梨大学)が中心になって企画運営していただき、とても有意義な見学会となりました。この場を借りて感謝いたします。また、翌日にはオプショナルツアーで、午前中はバスにてマルス穂坂ワイナリーを訪問し、ワイナリー長の茂手木大輔氏からご説明を頂きながら工場見学、試飲(有料でしたが、とてもおいしくいただきました)、買い物(お土産のワインを買われた方も多かったです)をいたしました。また、午後には韮崎大村美術館を見学し、最後は韮崎駅にて解散するという、こちらもとても充実した企画でした。研究の第一線の先生方のお話を聞けたり、ラボを見学できたりするのも技術士の企画ならではです。来年度以降の見学会も期待します。
(記録者:吉田 聡)
このページのお問い合わせ:生物工学部会
「IPEJ」,「日本技術士会」,「技術士会」,「CEマーク」及び「PEマーク」は、公益社団法人日本技術士会の登録商標です。
公益社団法人 日本技術士会 / Copyright IPEJ. All Rights Reserved.